外国人向け「経営・管理ビザ」制度が改正へ 大阪市民泊の新規受付停止も!?変化の波が迫る大阪不動産市場の今後を徹底分析
はじめに:大阪の不動産市場に起きている“静かな地殻変動”
2025年秋、外国人投資家や事業者にとって大きな節目となる動きが続いています。
一つは、外国人向けの「経営・管理ビザ(投資・経営ビザ)」制度の厳格化。
もう一つは、大阪市における特区民泊の新規受付停止の報道です。
どちらも一見「行政手続きの話」に見えますが、実は大阪市内の不動産市場に直接影響を与える“構造変化”の要因です。
本記事では、これら二つの制度改正をわかりやすく整理し、「大阪の不動産価格」「投資需要」「住宅市場」への具体的な影響を、データ・制度・心理の3視点から分析します。

第1章 外国人向け「経営・管理ビザ」とは?制度の基礎と改正の背景
まず押さえておきたいのが、「経営・管理ビザ」とは何かという点です。
1. 経営・管理ビザとは
日本で会社を設立し、自ら経営や管理に従事する外国人が取得できる在留資格のひとつです。
例えば、海外の投資家が日本で不動産を購入し、賃貸・運営・民泊などを事業として行う場合にも、このビザが必要になるケースがあります。
取得条件の一例は以下の通りです。
- 資本金が 500万円以上
- もしくは 常勤職員2名以上の雇用
- 実際に事業が稼働していること
- 事業所(オフィス)を実体として構えていること
この制度は「外国人起業家を支援する」目的で設けられたもので、過去10年で大阪・東京・名古屋などに多くの外国人事業者が進出しました。
2. なぜ制度改正が進められるのか?
しかし近年、このビザを悪用したケースが増えています。
「形だけの会社」を設立してビザを取得し、
実際には事業を行わず不動産を保有・転売する——いわゆるペーパーカンパニー利用です。
こうした問題を受けて、出入国在留管理庁(入管庁)は制度の厳格化を検討中。
その柱が、次の3点です。
| 改正項目 | 現行制度 | 改正方向(案) |
|---|---|---|
| 資本金要件 | 500万円以上 | 3,000万円以上に引き上げ |
| 雇用条件 | 職員2名または資本金要件 | 1名以上の常勤雇用を必須化 |
| 経営経験 | 不問 | 3年以上の経営経験またはMBA等学位必須化 |
昨日、2025年10月16日に施行されました。
つまり今後、資力・実務経験がない外国人投資家の参入は難しくなるということ。
大阪市内の投資用不動産市場においても、これは大きな意味を持ちます。

第2章 大阪市の「特区民泊」新規受付停止へ 背景と行政判断の狙い
続いて、大阪市の民泊(住宅宿泊事業)に関する動きです。
1. 特区民泊とは?
大阪市では「国家戦略特区」を活用し、民泊営業を通常よりも緩和して行える制度=特区民泊を導入してきました。
ホテル規制の緩いこの制度は、訪日観光客増加と相まって多くの外国人投資家が利用してきました。
特区民泊は通常の民泊よりも柔軟に運営が可能で、
たとえば180日制限がない、宿泊日数を短縮できるなどの特徴がありました。
2. なぜ新規受付を停止するのか?
大阪市保健局などの調査では、特区民泊に関する苦情・トラブル件数の増加が顕著です。
- 騒音・ごみ出しトラブル
- 無許可営業
- 近隣住民の生活環境悪化
- 管理不在のまま放置されるケース など
また、全国の特区民泊の約95%が大阪市に集中しており、市内一部地域では事実上の「民泊密集地帯」が形成されているのです。
そのため市は、2026年度以降の新規受付を段階的に停止する方向で調整に入りました。
既存の認可民泊は引き続き営業できる見込みですが、再認定時の条件見直しや厳格化は避けられません。

第3章 制度改正と民泊規制 大阪市の不動産市場にどう影響するのか?
ここからが本題です。
この2つの政策変更が、大阪市の不動産市場に与える影響を分野別に見ていきましょう。
1. 投資用不動産(民泊・収益物件)への影響
まず最もダイレクトに影響を受けるのが、民泊運用を前提にした収益物件です。
民泊規制と外国人参入抑制が重なれば、
「民泊利回り」を武器にした投資スキームは成立しづらくなります。
これにより以下の現象が予測されます。
- 民泊想定利回り10%前後 → 6〜7%程度に低下
- 一棟アパート・小型マンションの売却価格が 5〜15%下落
- 物件の入札競争が減少し、取引スピードが鈍化
一方で、既存認可済みの特区民泊物件は「プレミア価値」が付く可能性もあります。
新規が止まる分、認可済み物件の希少性が高まるためです。

2. 外国人投資家需要の減少と国内買い手への転換
「経営・管理ビザ」改正による資本金引き上げは、
外国人が不動産経営目的で日本進出する際のハードルを大きく高めます。
これにより、特に次の層が減少すると考えられます。
- 不動産保有を通じてビザを維持していた層
- 小規模な不動産投資(ワンルーム・区分マンション中心)層
- 資産形成を目的に日本不動産を保有していたアジア系投資家層
これらの買い手が減ると、**外国人投資マネーで価格が支えられていた大阪中心部(ミナミ・難波・心斎橋など)**では、需給バランスがやや緩みます。
ただし、国内の富裕層・法人投資家による「代替買い」は一定数見込めます。
日本人投資家にとっては、**高騰した物件価格が適正化される“買い場”**になるかもしれません。

3. 一般住宅・賃貸市場への影響
一方で、規制強化は住宅市場の安定化にもつながる側面があります。
これまで投資用に買われていた物件が、通常の居住用・賃貸住宅として市場に戻るケースが増えれば、賃貸住宅の供給量が増加し、家賃の高騰を抑える効果が期待されます。
また、民泊用に転用されていた住宅の一部が再び“居住用”に戻ることで、地域の騒音・ゴミ問題なども軽減され、居住環境が改善されるでしょう。

4. 不動産価格への中期的影響
制度変更の直接効果として、2026年以降の大阪市内価格動向は次のように推測されます。
| 地域 | 短期(〜2025年) | 中期(2026〜2028年) |
|---|---|---|
| 中央区・浪速区(民泊集中地) | 若干の調整(−3〜5%) | 安定推移または横ばい |
| 北区・西区(商業中心) | 小幅調整 | 投資再活性で回復基調 |
| 東住吉・此花など郊外 | 影響限定的 | 住宅需要中心に安定 |
総じて、市場全体での暴落リスクは低いと見られます。
民泊・短期投資の過熱部分が整理され、健全化する方向に進む可能性が高いです。
第4章 投資家・事業者が今とるべき戦略
では、今後どう行動すべきでしょうか。
制度変更期は「動いた人」と「様子見した人」で大きく差がつくタイミングです。
1. 申請や投資を急ぐなら“今”がリミット
特区民泊の新規受付が停止される前に、申請準備を終えることが重要です。
行政書士など専門家と連携し、物件調査→図面→保健所申請を早めに進めるのが得策です。
2. 収益モデルを「民泊依存」から「複合運用」へ
- 一部を民泊、残りを長期賃貸・マンスリーで運用する
- SOHO(住居兼オフィス)型やシェアスペース型へ転用する
- 不動産小口化・法人契約など多様な収益源を持つ
収益源を分散させることで、制度変更によるリスクを軽減できます。
3. 出口戦略を明確に
将来的に売却を想定している場合、“再販売可能性”が高い物件(駅近・再建築可・管理状態良好)を選びましょう。
規制下では流動性が下がるため、出口設計を最初から組み込むことが重要です。
4. 「法令適合」と「透明性」が投資価値に
入管制度や条例改正の動きは、今後さらに“実態重視”へシフトしていきます。
経営実態・雇用実績・事業計画の信頼性が求められる時代です。
裏付けのないスキームやグレーな運用では、
認可取消・事業停止のリスクを伴います。
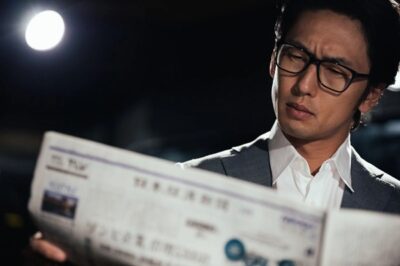
第5章 大阪不動産市場の今後:短期の混乱、長期の安定化
総合的に見ると、今回の2つの制度改正は
**「不動産市場の健全化」と「外国人投資の再構築」**を促すターニングポイントです。
- 短期的には取引量減少・価格調整が起きる
- しかし中長期的には、適正な価格と透明な市場が形成される
- 資本力・管理能力のあるプレイヤーが残り、市場品質が向上する
2025年〜2026年はまさに“選別の時期”。
表面的な利回りよりも、法令適合・運用力・地域貢献が問われるフェーズへと移っていきます。

まとめ:制度が変わっても「市場の本質」は変わらない
大阪市の不動産市場は、インバウンド・万博需要・再開発といったポジティブ要素も多く抱えています。
制度改正が一時的なブレーキになる一方で、市場の体力と基盤は依然として強固です。
むしろ、短期投資から長期安定運用へと転換する好機。
これから不動産を買う人、すでに保有している人、いずれにとっても「制度リスクを織り込んだ堅実な運用」が成果を分ける鍵となります。
不動産売買等でのよくある質問
Q1. 外国人でも今後、不動産を購入できますか?
はい、購入自体は可能です。制度改正は「ビザ取得」に関するものであり、所有権の制限ではありません。ただし「経営目的」の場合は要件が厳しくなります。
Q2. 特区民泊の営業はすぐに止まりますか?
すぐに一斉停止されるわけではなく、今後1〜2年の移行期間が想定されています。既存認可物件は継続可能な見込みです。
Q3. 今から民泊物件を買っても遅くないですか?
停止前の申請が間に合えばまだチャンスはあります。ただし今後の運営リスクを十分にシミュレーションしておくことが大切です。
Q4. 民泊ができなくなった物件はどう活用すべき?
通常賃貸・マンスリー運用・法人向け宿泊など、複数用途の運用で安定収益化を図るのがポイントです。
Q5. 市場は下がりますか?
一部地域では一時的な価格調整が予想されますが、全体として暴落は考えにくいです。市場の健全化による安定化がむしろ期待されます。

