🏠2024年7月改正:居住中の長屋でも“低廉な空き家等特例”の対象?――33万円仲介手数料の正しい理解と旧制度との違い
はじめに
2024年7月1日から、不動産の仲介手数料制度が大きく変わりました。
国土交通省による「低廉な空き家等に係る媒介報酬特例制度」の新設により、売買価格800万円以下の物件については、従来の上限を超えて税込33万円まで仲介手数料を受け取ることができるようになったのです。
一見、「空き家限定の制度」と思われがちですが、実際は違います。
制度上は「使用の状態を問わない」とされ、居住中の物件でも条件を満たせば対象になる可能性があります。
本記事では、
- 改正前後の仲介手数料の仕組み
- 居住中の長屋が対象になるか
- 売主・買主双方への影響
- 説明義務や悪用リスク
を、法令根拠と実務の両面から詳しく解説します。
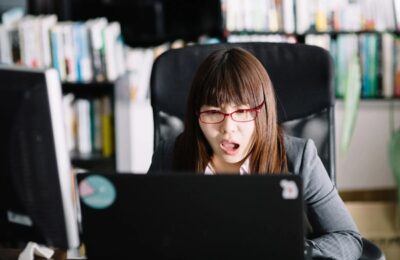
1. 改正の背景:低価格物件の流通を止めていた“採算問題”
ここ数年、地方都市や下町で「古い長屋」「老朽戸建て」「空き家」の売却が進まないケースが急増していました。
最大の理由は――“手数料が安すぎて、
業者が引き受けにくい” という現実です。
たとえば、売買価格が300万円や400万円の物件では、従来の制度では仲介手数料の上限が10〜15万円台にしかならず、現地対応や書類作成のコストをまかなえない業者が多かったのです。
そこで国交省は、空き家問題対策の一環として、低価格物件でも業者が積極的に媒介を引き受けられるよう、報酬上限を緩和する制度を導入しました。

2. 改正後の「低廉な空き家等特例」とは
▶ 対象物件
- 売買価格 800万円以下 の宅地・建物
- 「空き家」「長屋」「古家付き土地」「宅地」など
- 使用の状態(居住・非居住)は問わない
▶ 上限額
従来:報酬上限=売買価格×3%+6万円+税
改正後:税込33万円まで受領可能
▶ 適用条件
- 売主・買主の双方に対し「特例を適用する」旨の説明と合意
- 媒介契約書に特例を適用する旨を明記
- 宅建業法第46条の報酬規定改正(2024年7月施行)に準拠
3. 「空き家等」とは?――実は“居住中”も含まれる
国交省通達(2024年6月28日付)では、
以下のように記載されています。
「低廉な空き家等とは、800万円以下の宅地・建物であって、その使用の状態を問わないのをいう。」
つまり、「空き家であること」は必須条件ではなく、
居住中でも価格要件を満たせば対象になります。
“空き家等”という名称は制度上の便宜的な表現であり、実際には「老朽建物付き宅地」や「低価格住宅」も含まれます。
したがって、居住中の長屋でも
800万円未満であれば特例適用が可能です。

4. 改正前との比較:どれだけ変わった?
| 比較項目 | 改正前(旧制度) | 改正後(特例制度) |
|---|---|---|
| 対象 | 全物件 | 800万円以下の宅地・建物 |
| 上限額 | 売買価格×3%+6万円+税 | 税込33万円まで |
| 使用状態 | 問わず | 問わず(居住中でも対象) |
| 契約条件 | 通常媒介契約 | 特例適用の明記・説明義務あり |
| 買主負担 | 原則あり | 双方請求可(最大66万円まで) |
💡旧制度の正確な手数料計算
実は「3%+6万円」という表現は簡略式であり、正確には次のように価格帯ごとに料率が異なる累進制でした。
| 価格帯 | 料率 | 説明 |
|---|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5% | 小規模物件に対して高率設定 |
| 200万超〜400万円以下の部分 | 4% | 中間帯 |
| 400万円超の部分 | 3% | 一般的な住宅価格帯 |
つまり、300万円の物件では:
(200万円×5%)+(100万円×4%)=14万円(税抜)
これは「4%+2万円」とも言い換えられます。
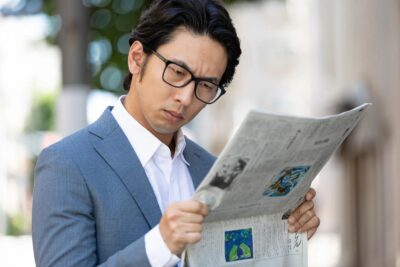
💰従来制度と特例の比較(具体例)
| 売買価格 | 旧制度上限(税抜) | 新制度上限(税込) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約14万円 | 33万円 | 約2.3倍 |
| 500万円 | 約21万円 | 33万円 | 約1.6倍 |
| 800万円 | 約30万円 | 33万円 | ほぼ同等 |
👉 特に300万〜600万円帯では「業者報酬が倍近く」になるため、低価格物件でも積極的に扱いやすくなりました。
5. 売主・買主双方に請求できる仕組み
この改正のもう一つのポイントは、売主と買主の双方から手数料を受け取ることが可能になった点です。
たとえば500万円の長屋を売買する場合:
- 旧制度
→ 売主:21万円+税
→ 買主:21万円+税
- 新制度(特例)
→ 売主:33万円(税込)
→ 買主:33万円(税込)
※双方に合意・説明がある場合に限る。
結果として、**最大で66万円(税込)**まで
報酬を得ることができます。

6. 注意:説明がない「空き家手数料」は業法違反の可能性
特例を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 媒介契約書に「特例適用」の明記
- 双方への説明と同意
- 宅地建物取引業法第34条の2(重要事項説明)に準拠
これらがないまま「空き家特例ですから33万円です」と口頭で説明するのは業法違反にあたる可能性があります。
「居住中なのに空き家扱いされた」
「書面に特例の記載がない」
という場合は、必ず契約前に根拠を確認しましょう。

7. 長屋・再建築不可物件が特例対象になりやすい理由
大阪市淀川区などの連棟長屋では、
- 接道義務(道路に2m以上接していない)
- 構造的に再建築不可
- 老朽化による修繕リスク
といった要因で、査定価格が数百万円台になるケースが多いです。
そのため、こうした物件は特例の800万円以下条件を満たすことが多く、制度的には対象になりやすいと言えます。
ただし、居住中の場合は必ず「説明・合意・契約書明記」が必要。
曖昧な「空き家扱い」はトラブルのもとです。

8. 悪用・誤用されやすいケース
- 「空き家等特例だから33万円が当たり前」と言われた
- 「居住中でも空き家扱い」と説明された
- 契約書に金額の根拠が記載されていない
こうした場合、「宅建業法第46条(報酬上限)」「第47条(不当表示)」に抵触する可能性があります。
9. 適正な業者の見分け方
✅ 契約前に「国交省報酬規定に基づいていますか?」と質問
✅ 媒介契約書に特例の明記があるか確認
✅ メールでも丁寧に説明してくれるか
✅ 33万円を一律で提示する業者は避ける
📩 フォローウィンドの無料相談
査定はメールのみで完結可能。
居住中の長屋でも「うちは対象?」
「手数料いくら?」を気軽に確認できます。

10. まとめ
| 項目 | 旧制度 | 改正後(特例) |
|---|---|---|
| 対象 | 全物件 | 800万円以下 |
| 手数料上限 | 累進制(5・4・3%) | 税込33万円 |
| 居住中の扱い | 通常居住用 | 対象に含む(要説明) |
| 買主負担 | あり | 双方請求可 |
| 注意点 | 書面説明不要 | 書面明記必須 |
よくある質問
Q1. 居住中の家でも特例対象?
→ 可能性あり。使用状態は問わない。
Q2. 契約書に特例記載がない場合?
→ 無効。業法違反の可能性。
Q3. 旧制度の計算は?
→ 300万円なら(200万×5%+100万×4%)=14万円(税抜)。
Q4. 特例を使えば必ず33万円?
→ いいえ。上限であり、実際は業務量・合意次第。
おわりに
「空き家特例33万円」は、低価格物件の流通を促すための制度です。
居住中の長屋でも対象となる場合がありますが、説明なしの請求は“違反の可能性”があることを忘れてはいけません。
焦らず、まずは「なぜその金額になるのか」を確認しましょう。
フォローウィンドでは、メール一本で
無料査定・制度の確認ができます。
あなたの“納得のいく売却”の第一歩は、
情報の透明性から始まります。

